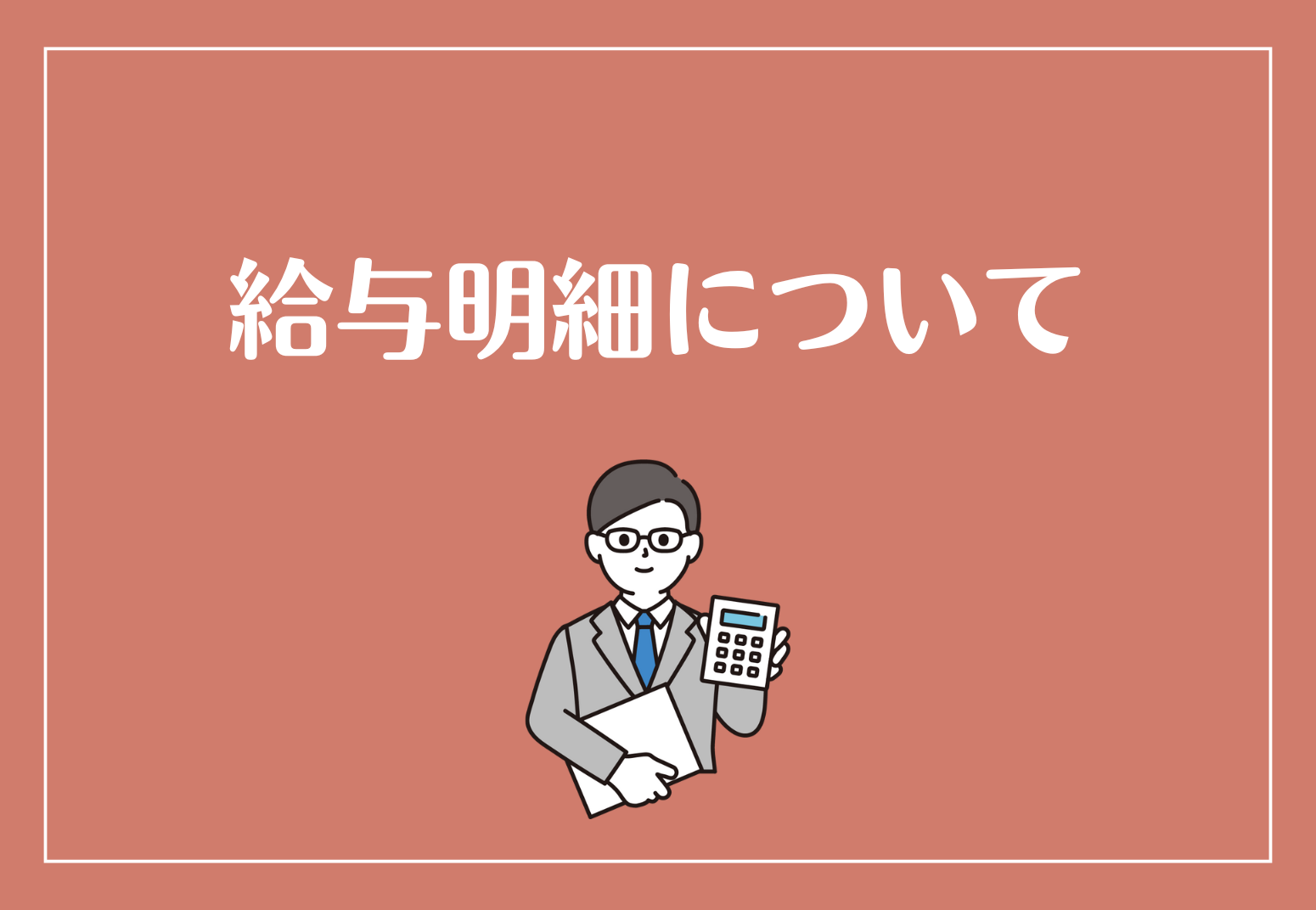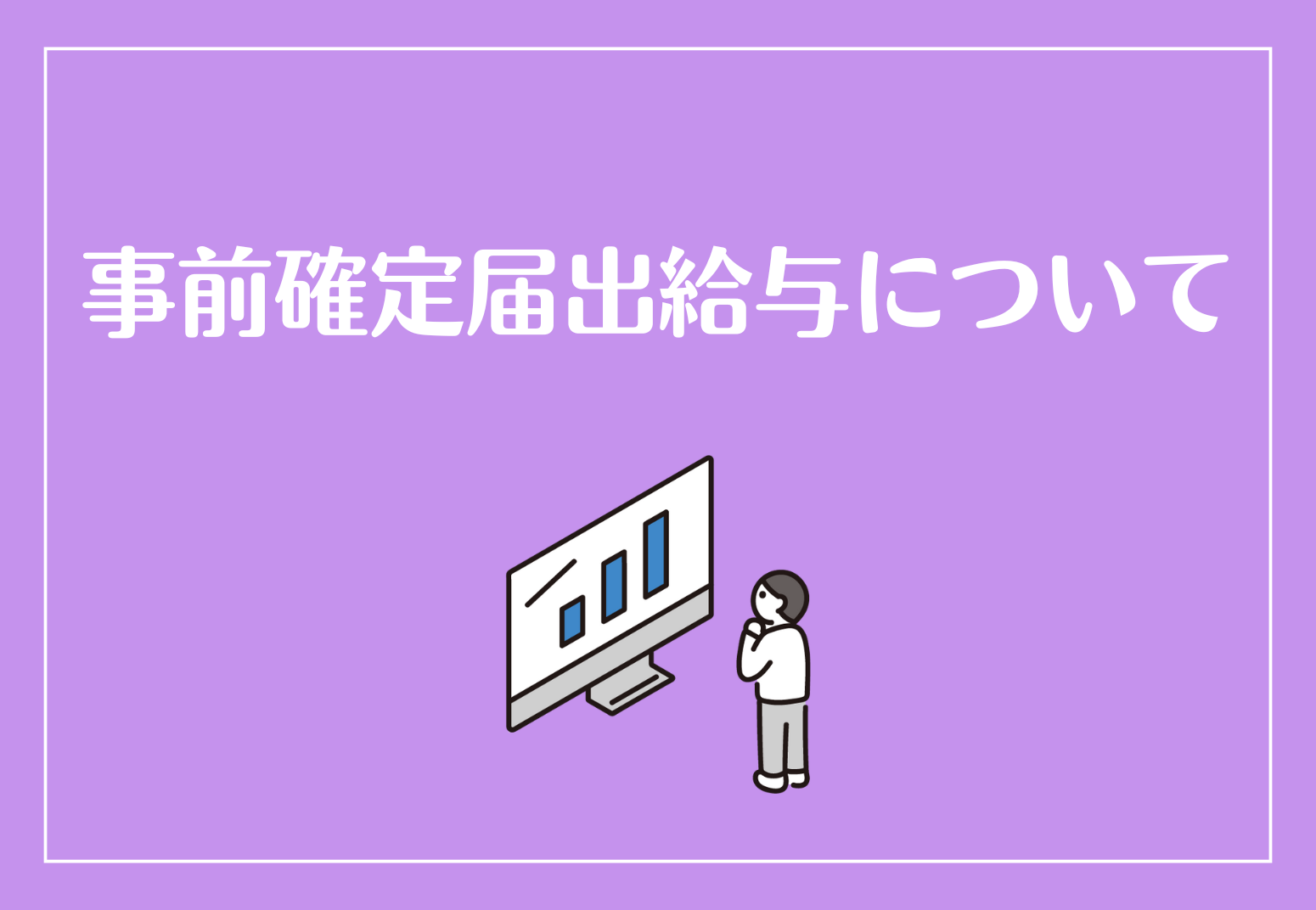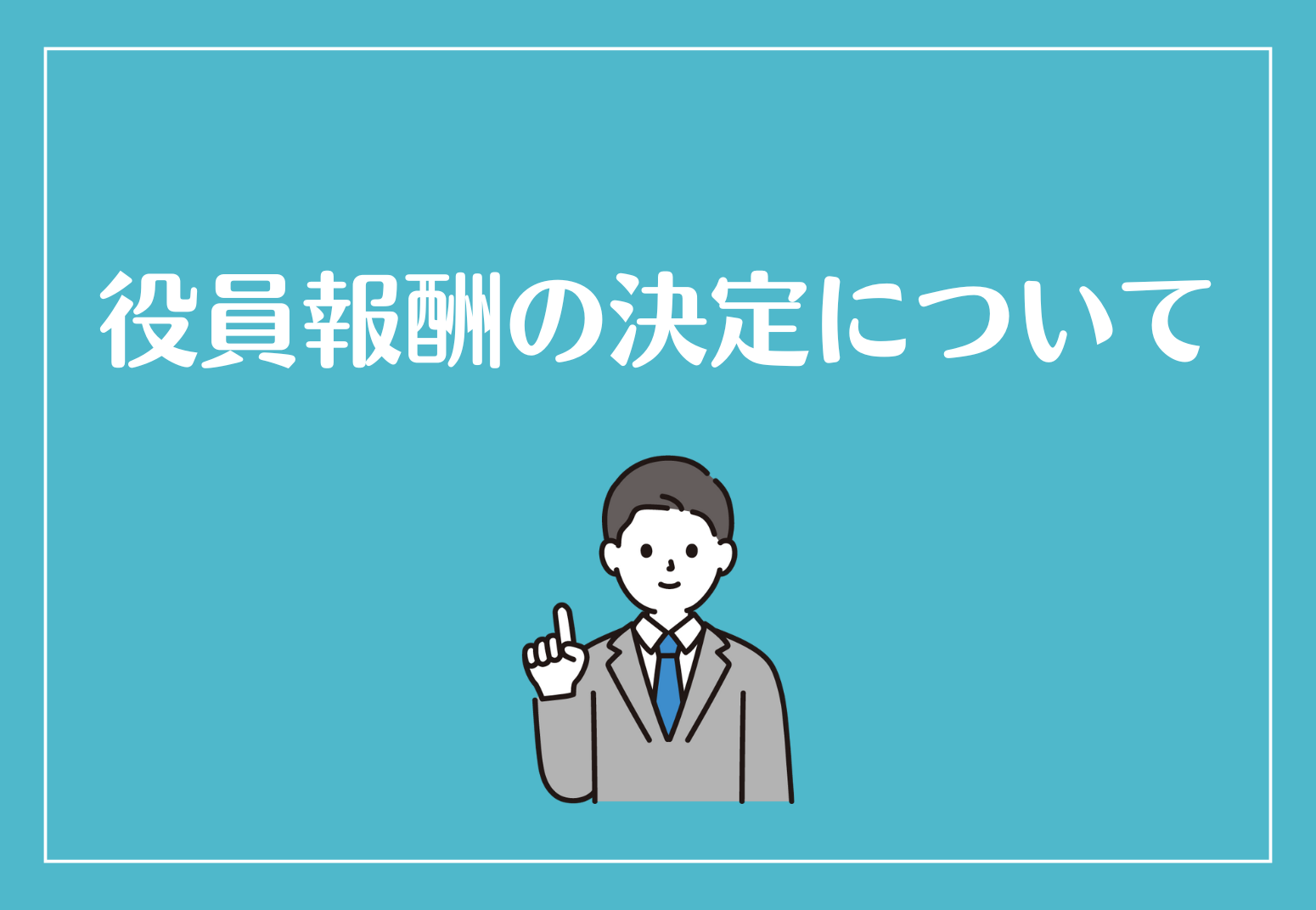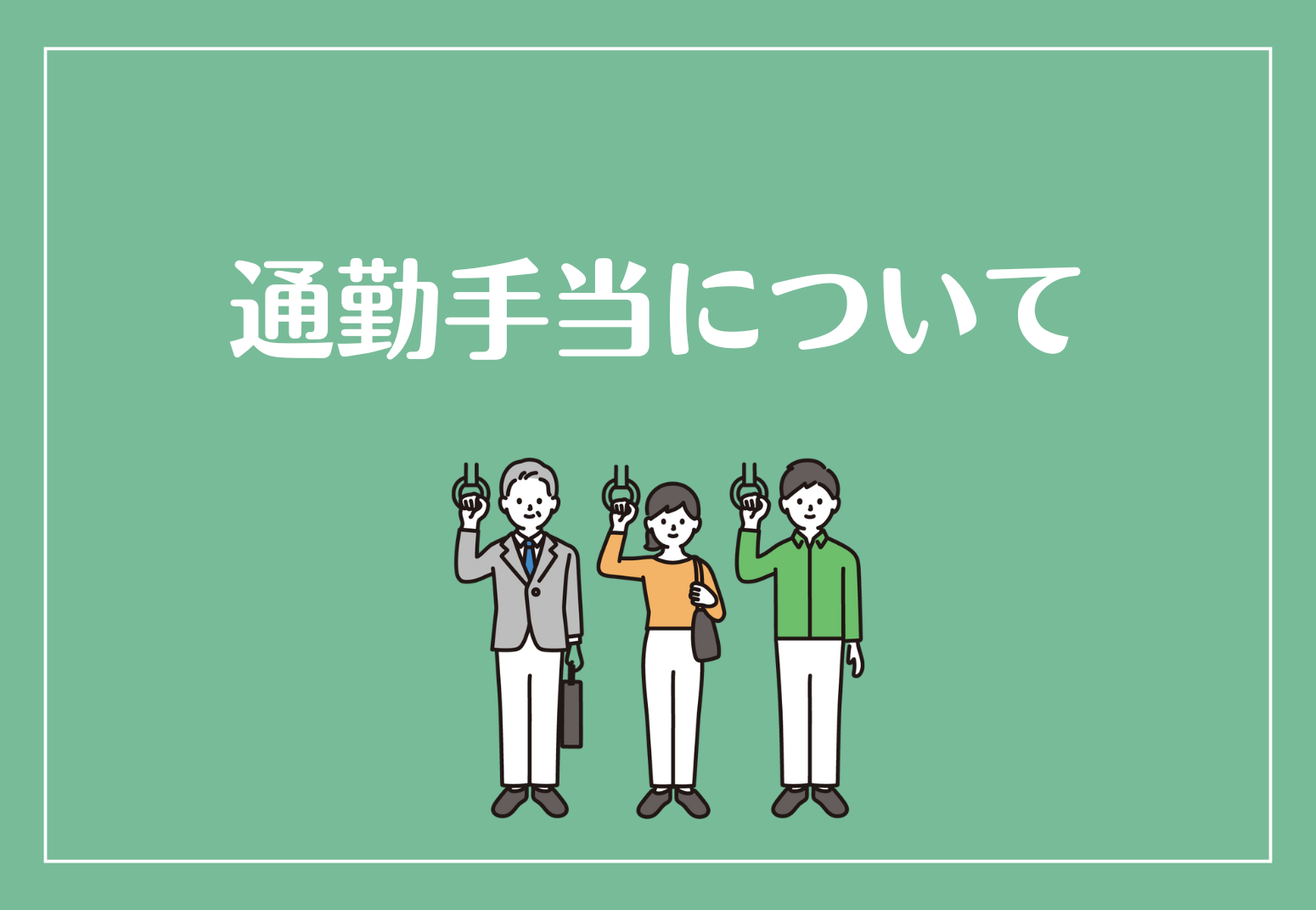
企業で働く従業員にとって、「通勤手当」 は重要な福利厚生の一つです。一方で、企業側も適切なルールのもとで通勤手当を支給する必要があります。今回は、通勤手当の基本や支給ルール、節税メリットなど をわかりやすく解説します。

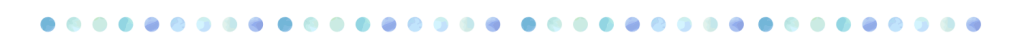
通勤手当とは?
通勤手当 とは、従業員が自宅から勤務先まで通勤する際にかかる交通費を、企業が補助するために支給する手当のことです。法律では通勤手当の支給は義務付けられていません。支給しなくても”法律違反ではない”ということになります。一般的に多くの企業では、公共交通機関(電車・バスなど)の定期券代 を基準に支給することが多く、自家用車や自転車での通勤 に対しても一定のルールで支給される場合があります。また会社によっては、通勤手当に上限額を設けている場合があります。支給される金額やルールは企業によって異なるため、就業規則などで確認することが重要です。
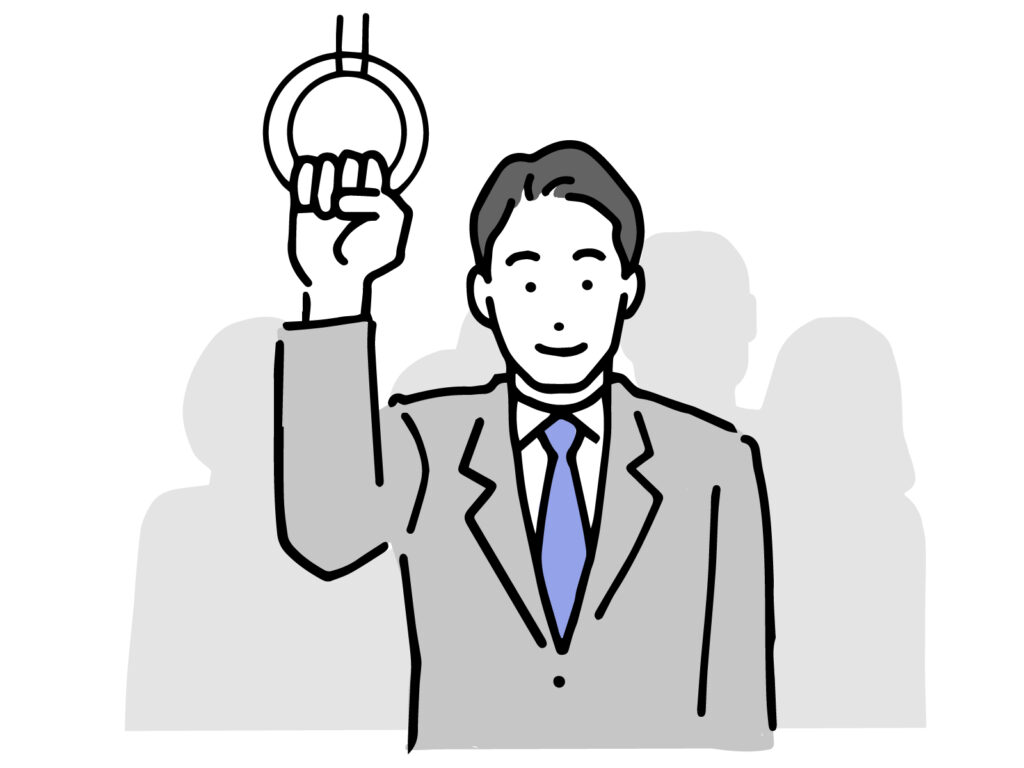
交通費と通勤手当との違い
交通費と通勤手当は、どちらも「移動にかかる費用」を指しますが、意味や使われ方に違いがあります。
交通費
交通費は、業務上の移動(出張や営業活動など)にかかった費用のことを指します。社員が自宅から職場へ通う場合ではなく、仕事上で電車・バス・タクシーなどを使って別の場所へ行く際の費用です。 例:東京から大阪への出張で新幹線を利用 → その運賃が「交通費」
通勤手当
通勤手当は、従業員が自宅から職場へ通うための費用として企業が支払うお金です。毎月一定額を支給するケースが多く、給与明細に「通勤手当」として記載されます。
例:自宅から会社まで電車で通う → 毎月の定期代として「通勤手当」が支給される
| 対象の移動 | 備考 | |
|---|---|---|
| 交通費 | 出張や営業活動など業務中の移動 | 実費精算されることが多い |
| 通勤手当 | 自宅と職場の通勤 | 給与と一緒に毎月定額支給が多い |

企業が通勤手当を支給する理由
1. 福利厚生の充実
通勤にかかる負担を軽減することで、従業員の満足度を向上 させ、定着率を高めることができます。
2. 人材獲得
通勤手当は、採用活動において、企業が候補者に提示できる魅力的な条件の一つです。特に、競合他社が手当を支給している場合、自社が支給しないと人材獲得において不利になる可能性があります。
3. 交通費の非課税措置を活用
通勤手当には一定額まで所得税がかからない(非課税) というメリットがあり、従業員の手取り額を増やしつつ、企業側の負担を抑える ことができます。

通勤手当の非課税限度額
通勤手当は、一定額まで所得税がかからない(非課税) という制度があります。
非課税となる限度額(2024年現在)
| 通勤手段 | 非課税限度額 |
|---|---|
| 公共交通機関(電車・バス等) | 月15万円まで |
| 自転車・バイク・自家用車通勤 | 1kmあたりの距離に応じた限度額 (例:2km以上10km未満は4,200円) |
企業がこの非課税限度額を超えて支給する場合、超過分は給与として課税対象 になりますので注意が必要です。

通勤手当におけるガソリン代の決め方
自家用車で通勤している従業員に通勤手当としてガソリン代を支給する場合、企業では以下のような方法で支給額を決定するのが一般的です。
距離に基づく計算方式
自宅から職場までの「片道距離」または「往復距離」に基づいてガソリン代を算出します。
使用する主な計算式:支給額 =距離 × 出勤日数× ガソリン単価 ÷ 車の燃費
通勤手当の支給ルールを決めるポイント
企業が通勤手当を支給する際は、明確なルールを設定 しておくことが重要です。
- 支給対象者の範囲(パート・アルバイトにも支給するか?)
- 支給額の上限(会社が負担する最大額を決める)
- 支給方法(毎月支給 or 半年分まとめて支給)
- 交通費の確認方法(定期券のコピー提出を求めるか?)
- 車・自転車通勤のガソリン代・駐車場代の扱い
社内の就業規則や給与規程に明記し、従業員に周知 しておくことが望ましいです。

こんな場合はどうなる?通勤手当に関するQ&A
Q1. テレワークが増えた場合、通勤手当はどうする?
会社の判断による ため、一部の企業では「出勤日数に応じて支給する」などのルールを設けています。最近では「通勤手当を廃止し、在宅勤務手当を支給する」企業も増えています。
Q2. 途中で引っ越した場合、通勤手当は変更できる?
通勤経路が変わるため、会社に速やかに申請する必要があります。企業側は、新しい通勤経路に応じて手当を調整しなければなりません。
Q3. 会社の都合で転勤になった場合、通勤手当の扱いは?
会社の指示による転勤の場合、通勤手当の増加分を会社が負担するのが一般的 です。ただし、個人的な理由での引っ越しは対象外となる場合があります。
Q4. 実際とは異なる経路や交通機関を申告し、高額な通勤手当を受け取っていたら?
故意に虚偽の申告を行い、実際より高額な通勤手当を受給していた場合は、不正受給とみなされる可能性があります。就業規則に基づき、差額の返還や懲戒処分の対象となる場合もありますので、正確な通勤経路・交通手段を申告することが重要です。
Q5. 実際には定期券を購入していないにもかかわらず、通勤手当を受け取っていたら?
実際に定期券を購入していない場合でも、合理的な理由があるときは通勤手当が支給される場合ありますが、基本的には定期の購入が必要です。購入していないことを隠して受給していた場合は、不正受給とみなされる可能性があります。
Q6. 非課税限度額を超える支給を受けていた場合の対応は?
通勤手当には所得税法上の非課税限度額が定められており、これを超える部分については課税対象となります。超過分は給与として課税され、源泉徴収の対象となるため、適切な処理が必要です。会社・従業員ともに税務上の取扱いに注意してください。
Q7. 就業規則で定めた通勤手当支給条件と、実際の支給に違いがあった場合は?
就業規則と実際の運用に相違がある場合は、速やかに見直しを行うことが望まれます。社員に不公平感が生じるほか、労使トラブルの原因となる可能性もあるため、実態に即したルールの整備と周知が重要です。
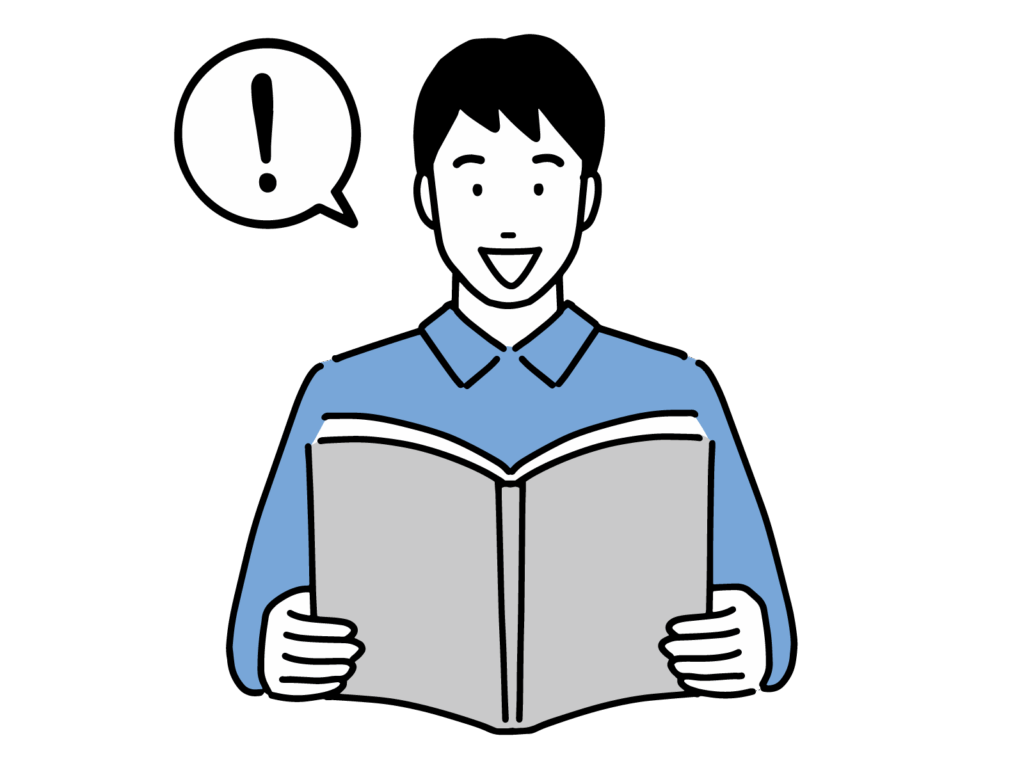
まとめ
- 通勤手当は、企業が従業員の通勤費用を補助する手当 であり、一定額までは非課税扱いになる
- 支給ルール(支給額・対象範囲・確認方法)を明確にすることが重要
- テレワークの増加により、支給方法を見直す企業も増えている
- 通勤経路の変更や転勤など、特殊なケースにも対応できるルール作りが必要
通勤手当は、従業員の働きやすさを向上させ、会社の魅力を高める大切な制度 です。
企業側も適切なルールを設定し、従業員が安心して通勤できる環境を整えていきましょう!